📝はじめに
「あと1回やったらおしまいね」「次で最後ね」
そんなふうに“予告”すること、みんな自然とやってるかもしれません。でもこれ、子どもにとってはとっても大切な声かけなんです。
今日は、子どもとの関わりの中で「予告すること」がどうして大切なのか、実際の場面とともに書いていきます✍️
🧠どうして“予告”が大事なの?
子どもにとって「先の見通しがある」ことは、安心につながります。
逆に、急に「もうおしまい!」とか「ダメでしょ!」って言われると、心の準備ができていないからパニックになったり、ぐずったりしやすくなります。
🎵実際の場面①:練習の終わりを予告する(その回数で必ず終わる)
楽器やダンスの練習中。「あと3回やってみようか」と予告しておくと、
子どもは「あと何回で終わるんだ」とわかるから、がんばりやすくなります。
特に、できなくてイライラしてるときは「いつ終わるかわからない」不安があると余計につらくなるけど、「あと3回やってみよう」と決まっていれば、踏ん張りがつきます。絶対やってはいけないのは、3回といったら絶対3回で終わること。おまけはつけません。
子どもだけでなく、一緒にその場にいる人にも見通しを共有することも大事です。
😠実際の場面②:叱るときの予告(観察する目も大事)
発達に課題のある子どもたちは、注意されることを多々します。でも、ボディイメージがなかったり、その場の判断ができなかったりと、状況はさまざまです。なので、「わざと」なのか「しょうがなく」なのかをこのように判断します。
たとえば、こんな流れ👇
- 1回目:「たまたまかな?」と様子を見る。
- 2回目:「さっきもやってたね。もう1回やったら注意するよ」と審議&予告。
- 3回目:予告どおりに「それはダメ」と伝える。
ここで大事なのは、「怒るって言った側も、本気で見守る覚悟を持つこと」。
ただの“脅し”になってしまわないように、
ちゃんと子どもの様子を見ていて、必要なときにしっかり関わる姿勢が大切。
💡“予告”のコツ
- 数字を使う(あと〇回、〇分後など)
- 子どもの年齢に合わせた言葉選び
- 必ず「予告どおりにする」こと(信頼につながる!)
✨おわりに
「あと〇回ね」「もうすぐおしまいだよ」といった予告の声かけは、
子どもたちの“こころの準備”を助けてくれる、魔法のような言葉。
日常の中で当たり前にやっていることかもしれないけど、
ちょっと意識して続けていくと、子どもとの関係がぐっとスムーズになるかもしれません☺️

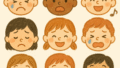

コメント