教育現場でよく耳にする「対話」。「会話」とは、何が違うのでしょうか。一緒に考えてみましょう。
🔍 AIに聞いてみた「会話」と「対話」
まず、AIにそれぞれの言葉の意味を聞いてみました。
Perplexityによる定義:
- 会話:相手が1人とは限らず複数人での雑談、情報交換も含む。必ずしも、相互理解を目的とせず日常の軽いおしゃべりなどが中心で浅く広い内容が多い。
- 対話:基本的には2人が向かい合って話すことを指し、お互いの意見・感情・価値観のずれを理解し合い、相互理解を深めることが目的。
ChatGPTによる定義:
- 会話:テンポよく交わされる日常的なやりとり。
- 対話:じっくり向き合うキャッチボール。ボールが返ってこなくても、投げることそのものが大切。
👀 支援の現場から考えてみると…
授業やトラブル対応の場面では、「相手と理解し合う」ことが求められます。
その意味で、相互理解を目指す“対話”はとても重要です。
でも、特別支援の現場では、そもそも**「会話」が成り立たない子どもたちもたくさんいます。
言葉が出づらかったり、伝えたいことがうまく言語化できなかったりする子どもたちにとって、“会話の前段階”から丁寧に積み重ねていく支援**が必要なんですよね。
🧸 私の経験から:クレーン現象と“ことばの獲得”
たとえば、自閉スペクトラム症の子どもたちに多く見られる「クレーン現象」。
これは、言葉の代わりに大人の手を引っ張って、自分のやりたいことを伝える行動です。
こんな時、私は**「言わせる」ことを大切にしてきました**。
例)
おもちゃを出してほしい → 手を引っ張って私をおもちゃ箱まで連れていく
→ 私:「おもちゃ出してほしいのね」
→ 子:「(言葉が出ない)」
→ 私:「なんて言うのかな?」
→ 子:「おもちゃ取って」
→ 私:「いいよ」と言って渡す
このように、【状況+言葉】をセットで伝え、「伝わるって嬉しい!」という経験を積んでもらうようにしています。
これは、外国語を覚えるときにも似ていて、「意味ある状況の中で言葉を結びつける」ことが習得の鍵になると感じます。
💬 さいごに
「会話」も「対話」も、子どもたちにとっては社会の中で生きるための土台です。
とくに、まだ言語の発達が未熟な子どもたちにとっては、まず伝わる楽しさを感じることが第一歩。
そのためにも、大人が丁寧に受け取り、必要な言葉を添え、安心してやりとりができる関係性を築くことが大切だと思います。

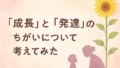
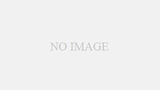
コメント