学校生活での「困りごと」って?
〜3つの視点から考える支援のヒント〜
学校での生活がうまくいかない子どもたちを、どうサポートしたらいいのか。私は日々、その子の困り感に寄り添えるよう考えています。
最近、「支援が必要な場面」は、大きく3つの視点でとらえると整理しやすいと感じるようになりました。よかったら参考にしてみてください。
🌱どんなときに「支援」が必要なの?
学校では、子どもたちに「自分でできること」がたくさん求められます。保育園と違い、先生1人が見る人数が多く、生活面・行動面・学習面のちょっとしたつまずきが、大きな困り感に繋がることもあります。
そこで大切になるのがこの3つの視点です。
① 日常生活の支援
身の回りのことが、スムーズにできるか?
例えば…
- 着替え:裏表を正しく着る、たたむ、最後までやりきる
- 食事:出されたものを自分で食べる、食具の使い方、おかずの大きさの調整
- 排泄:行きたくなったら言える、タイミングを見てトイレに行ける、拭くなどの処理ができる
② 行動の支援
集団の中で「自分をコントロールする力」が必要になります。
- 列に並ぶ、順番を待つ
- 手を挙げてから発言する
- 次の指示を聞く、メモを取る
- 衝動を抑える、時間を守る
- 友達とやりとりができる、建設的な意見を伝えられる
- 不安を言葉で伝えられる、自分でクールダウンできる
③ 学習の支援
学びの入り口に立てているか、も大切です。
- 自分や家族の名前を言える
- ひらがな・カタカナの読み書き
- 数の理解・計算
- 学年相応の授業に参加できる
- 学力テストに取り組める
🔍まとめ:困り感の背景にあるものを見つけよう
子どもたちが「困っているとき」、同時に先生も「どう対応したらいいのか」と悩むことがあります。
大切なのは、「いつも困っていることは何か?」「どんな場面で、どんな先生でも困るのか?」を整理すること。
それが、適切な支援への第一歩になります。
🧡 保護者の皆さんへ
子どもの困り感には、必ず理由があります。「何が苦手なのか」「どんな工夫ができるか」を一緒に見つけていけたら嬉しいです。

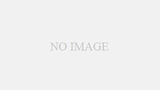
コメント