教室で伝えたはずのことが、伝わってなかった…って経験ないですか?
実はこれ、子どものワーキングメモリ(作業記憶)に関係しています。
人間の脳は、一度に処理できる情報の量が決まってる。
だからこそ、大人が「短く」「具体的に」伝えることが大事です。
📝教育実習で教わった「1(いち)指示1(いち)行動」
まだ先生になる前、教育実習で教わったことがあります。
「1つの指示に、1つの行動だけを伝えること」
たとえば…
❌「ノート出して、35ページって書こうか」
⭕「まず、ノートを開きましょう」→みんなが開いたのを確認してから「次に、『35ページ』って書きます」
この1ステップずつ分けて伝えるって、今でもめちゃくちゃ役立ってます。
✂️助詞を省く。リズムよく、短く言う。
実際に子どもたちに伝えるとき、私はよく助詞を抜いてキーワードだけに。
たとえば、運動会の集合前なら…
❌「いい?次の集合言うよ?持ってくるものは、水筒と赤白ぼうし。それで、入場門に並んでててくれる?」
⭕「水筒、赤白ぼうし、入場門、並ぶ」
短いからこそ、頭に残る。それが、行動につながってきます。
🎯短く言う=伝わる工夫
伝えるって、たくさん話すことじゃない。
必要なことだけを、必要な順番で、短く言う。
それが子どもの理解を助けて、行動を引き出す力になる。
✍️まとめ
- ワーキングメモリには限界がある
- 「1指示1行動」は、伝わる基本
- 助詞を抜いて、リズムよく言う
- 「伝える」は、「届く」ための工夫!


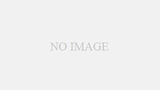
コメント